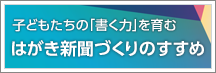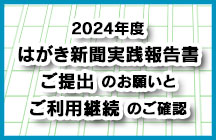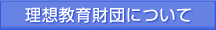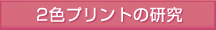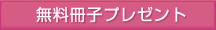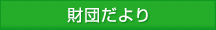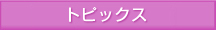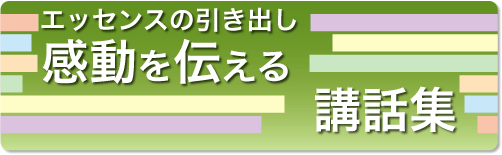 |
||||
「子どもたちが楽しみにするような感動的な話をしよう」というコンセプトのもとに、小学校の校長が月曜朝礼で話した87の講話から精選。歳時記、伝記、童話、民話、感動的な出来事、スポーツ、映画、演劇と話材のジャンルは幅広く、「学校だより」や「学級通信」を通して保護者の心にも響く題材として活用できるものが満載です。 <ご利用にあたって>
今年度もあとわずかになりました。1年生も入学当時と比べると、見違えるほど立派になりましたね。みなさんも、いろいろなことをこの一年で学んできました。勉強のことだけでなく、やさしく強い心を育ててきました。 今年の卒業生は、「聞き上手である」といわれています。在校生のみなさんは、ぜひ卒業生のよいところを引き継いでください。他人の話がきちんと聞けることは、より豊かに生きるためにきわめて大切なことなのです。 「口はわざわいのもと」ということわざがあるくらい、人間は他人の話を聞くことより、自分でおしゃべりがしたいのです。 人間の顔には、耳は二つありますが、口は一つですね。これには深い意味があるのです。人類誕生の一つの説に「人間の顔は初め脳でおおわれていた。長い間に脳が進化して顔になった。だから顔には、その人の考えていることがすべて表れる」ということがあります。 その進化のなかで、人間として必要に応じて目や鼻や耳や口ができました。そのとき、よく見えるように目は二つできました。そして、話をよく聞くように耳も二つできました。しかし、口は必要なことだけ話をすればよいので一つしかできませんでした。 しかし、子どもはおしゃべりなのです。そこでこれを子どもにあてはめると、どういうことかといいますと、お話を聞くときは、素早く聞く態勢を取る、つまり、けじめをつけるということになります。 楽しむときは思いっきり楽しむ、そして、話を聞くときになったら、静かに耳を傾けるということです。みなさんの勉強は、「聞く」ことによって学ぶことが多いのです。もちろん、本を読んで学ぶことも、体で体験して学ぶこともありますが…。 校長先生からのお願いですが、この学校の子どもは「聞き上手だ」といわれるようになってほしいのです。このことは、今年の卒業生から在校生が受け継いでほしい第一番の願いだと思います(中略)。 春休みがもうすぐですが、家族の人や友だちとすごすわけです。目で見るもの、耳で聞くものすべてが勉強になります。 (『小学校 心のとびらを開く月曜講話』青木靖著/学事出版より)
|